
(この記事は、2022年5月16日に配信しました第347号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回の「たのしい音楽小話」は、パイプオルガンのお話です。
オルガンと聞きますと、ある方はかつて小学校などにあった足踏みオルガンを、ある方はエレクトーンの事をイメージされるようですが、クラシック音楽の世界では、パイプオルガンの事を示します。
オルガン(パイプオルガン)は、ピアノよりも昔に作られた鍵盤楽器で、紀元前には既に存在していたという大変歴史がある楽器です。たくさんのパイプに空気を送り込んで音を出します。昔は、人力で空気を送り込んでいたようですが、現在では機械で空気を送り込み、音を出しています。
教会のミサなどに使われますので、主に教会に設置してありますが、ご存知の通り大きなコンサートホールにも設置されています。見た目にも音量にも圧倒される楽器ですから、ちょっと触ってみたいと思われる方も少なくないと思います。私も以前から、あの大迫力のオルガンが好きでコンサートにも行きましたし、ピアノでバロック期の作品を弾いていて、「これはピアノで弾くよりも、オルガンでじゃ~んと弾いた方がはるかに似合いそう」と思っていましたが、今春からオルガンのレッスンを受けることになりました。
実際にオルガンを弾いてみますと、なかなか大変な事が多く、ピアノとはだいぶ違うなあという印象を持ちました。少し例を挙げてみたいと思います。
ピアノは、88鍵の鍵盤が1列に並んでいて、右へ行くほど高い音、左へ行くほど低い音が出ます。オルガンも基本的には同じなのですが、オルガンのサイズによって鍵盤の列数が異なり、2段鍵盤や4段鍵盤などがあります。それにプラスして、足鍵盤もあります。ですから、ピアノは真ん中のドというと、1つしかなく体の真ん中より若干左側にあるわけですが、オルガンは複数あり当然体からの位置関係も異なってきますし、足鍵盤に至っては楽器の中央からかなり右側にあります。
右手、左手、足の3パートを同時に演奏しますので、楽譜もピアノとは異なり、常に3段譜になります。ピアノの場合、時たま3段譜がありますが、その場合ももちろん両手で弾きますよね。通常のピアノの楽譜で弾いてみると、3パートの曲だったという事もあります(バッハのシンフォニアなど)。
足は、両足で1パートを演奏するのですが、ピアノの指番号のように、どちらの足で演奏するのかを決めておかないと、大変な事になります。いつも交互に使うわけでもなく、でもエレクトーンのように左足ばかりでもありません。しかも、2オクターブ以上の足鍵盤を自由自在に両足で弾きこなすことは、本当に至難の業で四苦八苦します。
指で弾く鍵盤の方は、曲のスタイルなどによって、ピアノのように同じ列の鍵盤を両手で弾く事もあれば、右手は上の方の鍵盤、左手は下の方の鍵盤を弾くこともあり、場合によっては左手が上の方の鍵盤という事もあります。鍵盤の列ごとに音色を変えますので、フレーズの音楽の特徴を踏まえて、鍵盤を選ぶようです。左右で弾いている鍵盤の高さが異なるので、慣れるまでは何となく不思議な感じがします。エレクトーンを弾いたことがある方は、スムーズに演奏できるのかもしれませんね。
そして、オルガンを弾き始めて感じる最大の難関が、足が左手につられてしまうという事です。ピアノの場合、右手は高音部、左手は低音部に分かれて、主に右手でメロディーを、左手で伴奏を弾きます。ですがオルガンは、常に右手、左手、足の3本を同時に使い、左手と足が低音のようになります。もちろん足鍵盤の低い音はとてつもなく低い音も出せますが、同じような音域を使うので、今出ている音が左手で弾いている音なのか、足で弾いている音なのか、また次の音はどちらで何の音を弾くのか、ごちゃまぜになってきます。そもそも、足鍵盤自体もちらちら見ながら弾いているわけですから、ずっと楽譜を見て弾くわけにもいかず、ますますこんがらがってきます。このような状況は、オルガンの先生曰く、あるあるなのだそうです。そのため、ピアノで練習をして手だけでは暗譜で弾けるくらいにしておいても、いざオルガンで弾きますと、あちこち間違いだらけで、最終的には自分が何をやっているのかも危うくなってくるのです。
このように、オルガン初心者の私が弾くと、まるで格闘技のような優雅さのかけらもなく単に音を出すだけの間違えずに弾ければ上出来みたいな演奏になり、レッスン中は冷や汗をかきっぱなしで、終わるとヘロヘロになっています。
さて先日、オルガンの先生がリサイタルをなさるという事で聴きに行ってみました。会場は、コンサートホールではなく大学の中にある礼拝堂で、それだけでなんとなく厳かな気分になるものですね。
前半がバロック期の作品で、後半が近現代の作品というプログラムになっていました。バロック期のオルガンの作品は、普段ピアノでバッハなどを弾いている時と同じような感じなので、聴きやすく、ピアノではいろいろな声部(パート)を指のタッチで音色を変えるところを、オルガンでは、フルートの音の次にオーボエの音などのように、ダイレクトに音色がガラッと変わるので、ピアノよりもはるかにわかりやすくなります。
近現代の作品は、作品ごとにだいぶ変わるのですが、和音の響きがとても面白く、箇所によってはゲームのBGMの電子音をすごく高級感あふれる音にしたような雰囲気もあり、とても興味深かったです。
ピアノの音は、音が出ると後は自然に減衰していきますが、オルガンは音を出したときの強さのまま、減衰することなく音を出し続けることができるので、音の重なりがとてもよく聴こえます。
私は、大苦戦しながらオルガンを練習していますが、プロのオルガニストが演奏しますと、そのような格闘している様子は全くなく、涼しい顔で優雅に演奏していて、天から美しい音が降ってくるかの如く響き渡っていました。
近年では、大ホールなどで短時間のオルガンコンサートが開催され、無料だったりかなりお手軽な価格で聴くことができます。ピアノよりも古い歴史がある鍵盤楽器の音色を聴くことで、ピアノで弾くときの音色の工夫などに大変参考にもなるかと思います。ご興味のある方は、オルガン演奏会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
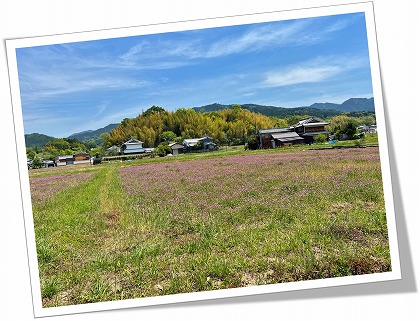
(この記事は、2022年5月2日に配信しました第346号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、ゴールデンウィーク前のピアノ教室の様子です。
ぽかぽか陽気の日もあれば、夏日もあり、そうかと思えば急に冷え込んで肌寒い日もあり、目まぐるしく天候が変わる今日この頃です。
数年ぶりの緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が無いゴールデンウィーク期間を迎え、生徒さん方からもお出かけの予定をちらほら聞くようになりました。そうは言っても、お子様の生徒さん方は、6月に発表会を控えていますので、楽しくお休みを過ごしていただきつつ、ピアノの練習にも精を出していただけたらいいなあと、少し欲張りな気持ちを抱いてしまいます。
発表会で大好きなアニメの曲を弾く生徒さんは、今週もご機嫌な様子でピアノを弾いていました。裏拍に音を弾くところが多いのですが、少し曖昧なタイミングで弾いている所があったり、少し音が飛ぶところで一瞬間が空いてしまっている所がありましたので、その個所を重点的にレッスンを行いました。相変わらず、「難し~い」やら、時には悲鳴のような雄叫びを上げたりもするのですが、受け止めつつも何回も反復練習を行い、正しいリズムを覚えることと、自分の演奏がきちんと出来ているのか否かを判別できるようにしました。
後ろで聴いているお母様が、レッスン後に「いや~、なかなか難しいリズムで、私はよくわからないのですが…大丈夫かしら?」と少し心配そうにお話をされていましたが、「レッスンでも何回も正しいタイミングで自力で弾けていますし、違うときに違うという事も聴き取れて修正できていますので大丈夫です」「ね、何回も成功していたもんね」と生徒さんに話を振りますと、「うんっ!」と力強く頷いていました。どちらかというと、自信満々で弾くタイプではないのですが、着実に完成に向かっていて頼もしいなあと思いました。
一方で、自信満々で弾くタイプの生徒さんは、かなり安定して楽しそうに発表会の曲を弾いていました。少し短めの曲を選んでいたこともあり、かなりまとまってきていましたので、「もう1曲、発表会で弾いてみましょうよ」と聞きますと、生徒さんも同席されているお母様も、パッと嬉しそうな笑顔を見せていました。候補の曲を数曲ご紹介して、それぞれの曲の解説や難易度などをお伝えし、聴き比べていただいたところ、少し面白いタイプの曲を選んでいました。
先日、初レッスンをしたのですが、楽譜を広げたところ、「あっ」というリアクションをしていましたので、「もしかして、思ったよりも長い曲で、選んだことを少し後悔している?」と冗談でお話したところ、少し苦笑されていました。どうやら、図星だったのかもしれません。「確かに、1曲目に比べると長いから、あら~と思うかもしれないけれど、曲の作りを見ていくとどうかなあ? 一緒に見てみましょ」という事で、楽曲分析(アナリーゼ)をしてみました。
場面で区切って番号を振ることを、いつも一番最初に行っています。生徒さんと一緒に考えながら曲を区切っていき、「あれ、これってなんだか聴き覚えがあるよね?」と尋ねると、「あっ、(1)と同じだー」「そうそう、全部同じなんだよね。だから、(1)番が弾けると、ここは練習しなくても弾けちゃうね」「ここは、(1)とほとんど同じなんだけど、高さだけ違うんだよね。1オクターブ高くして弾くだけだから、すぐ弾けそうだね」などと、ワイワイ楽しく分析をしていきました。終わった時には「な~んだ。難しそうだと思ったけれど、簡単じゃん!」と話していて、同席されていたお母様も、苦笑いをされているような様子でした。
早速、左手の伴奏の練習から弾き始めましたが、伴奏もパターンがありますので、それがわかるとかなり弾きやすくなります。生徒さんも、あっという間にわかり、伴奏の軽快な動きにノリながら楽しそうに弾いていきました。その後、生徒さんの左手の伴奏に、私がメロディーを弾いて、全体の音楽の流れや両手で弾いた時のイメージを掴むこともしてみました。
次に、右手のメロディーも少し練習をしてみましたが、変拍子の曲なので、音を伸ばした後の次に弾く音のタイミングが少し難しく、遅かったり速かったりしていましたので、「私が、3と数えたらこの音を弾いてね」とお話をして練習をしてみました。「あれっ? まだ2しか言ってないよ~」というと「あー!間違えたあー」と叫んだりして、なんだかだいぶ盛り上がった雰囲気でレッスンが終わりました。
初めて弾くタイプの曲なのですが、1回目からいろいろと曲が見えてきていますし、曲の特徴的な拍子感を割とすんなり受け入れているようですので、今後も順調に曲の仕上げまで進めそうな感じがして、私も楽しみです。
少し前から通っておられる80代後半の生徒さんは、お好きな曲を毎回熱心に練習をしているのですが、若干スランプ気味というのか、ジレンマを抱えている様子でした。ご自分で弾いていても、曲になっていない気がするそうで、「なかなか指も思うように動かないし、曲が難しいことは承知していたけど、この続きの変奏部分は難し過ぎて到底弾けない気もするし、自分も年だからここまでかと限界もわかっているんだけれど。以前習っていた先生からもらった簡単にアレンジした曲を弾いたら良いのかもしれないけれど、どうもつまらない気がして弾きたくないし。曲も、元々ピアノソロの曲ではないし、プロが演奏しているので、とっても速くてなんだか同じ曲を弾いているように思えない」というようなお話をされていました。
「今弾いている部分の先にある、変奏部分の数曲については、プロでもコンサートなどでは変奏を抜粋して弾く事もありますし、かなり難しくなるので、まずは今弾いている箇所までということにしましょう」というお話をしました。そして、曲には、ある程度適切なテンポ感があり、弾き慣れている最初の部分を少しテンポを速く弾く練習をすることで、曲のイメージに近づけることや、楽しみでピアノを弾いていらっしゃるので、無理に好きではないアレンジの曲を弾く必要は無いと思うという旨のお話もしました。
早速、少し速めのテンポで弾く練習をして、どの箇所に間が空いてしまっているのかをチェックして、正しいテンポで弾くとどのような音楽の流れになるのかも確認をしました。そして、「参考ということで、ちょっと私が弾いてみますね」と言って、弾いてみました。弾き終わりますと、「いや~、自分のとは全然違いますね。でも、これまで何人もピアノの先生にピアノを教えてもらいましたが、先生にピアノを弾いていただいたのは初めてなので。こういう風になるんですね。今日は、本当に良い日になりました」とおっしゃりながら、何回もお辞儀をしていました。「あら~、そうでしたか。なんならジャンジャン今後も弾きますので」とお答えをしますと、笑顔を見せていました。
ご高齢の生徒さんは特に、なかなか思うように指が動かず、ご自身がイメージする演奏とのギャップを感じてしまう事があります。それでも、日々の練習で、以前よりも指のコントロールは付いてきていますし、後は、イメージ通りの演奏にするための最適なアドバイスと、その練習を一緒に進めて行くことが必要となりますが、何よりも、生徒さんが感じている事やお気持ちに寄り添うことが大切なのだと改めて感じました。
生徒さんが、今後も日々の生活の楽しみとしてピアノと関われるよう、そしてずっと続けられるように、私も頑張りたいと思います。
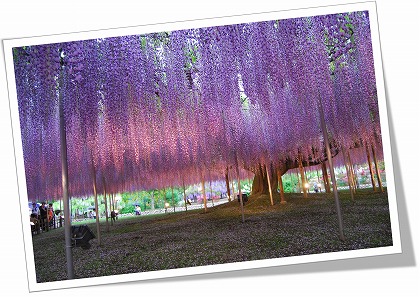
(この記事は、2022年4月18日に配信しました第345号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、春のピアノ教室の様子です。
春真っ盛りとなりました。ピアノ教室にいらっしゃる生徒さん方との挨拶では、「肌寒いですね」と話したかと思うと、「今日は結構暖かくなりましたね。というより、むしろ暑くなったと言った方が良さそうですね」と話したりと、会うたびに真逆の事を話している自分に気づきます。
お子様方は、春休みを終えて新学年となり、入学式を終えた生徒さんもいらっしゃいます。いよいよ、新生活のスタートです。小学1年生だった生徒さんは、若干しょんぼりした様子でレッスンに現れました。「今日、初めて6時間だった」と話していて、「ああ、もう2年生になったから、6時間授業になったのね。大変だった?」と声をかけました。「うん。学校から帰ってきて、急いでここに来たから、おやつを食べられなかった」とポツンと答えていました。6時間授業で疲れたから元気がないと思っていたのですが、そうではなく、どうやらおやつを食べられなかったことにしょんぼりしていたようです。それでも、ずらっと教材をピアノの譜面立てに並べ、楽譜を広げるなり、いつもの様子ですらすらと弾き始めましたので安心しました。
毎年、夏に行われるお子様の発表会の日程が決まり、今年は6月の開催となりました。想定より1ヵ月ほど早く行う事になりましたので、生徒さん方には発表会の曲を最優先で練習を進めるようにお話をしています。生徒さん方は、まだ譜読みの段階で、少々大変な時期ではありますが、それでも最終的に自分で選んだ曲でもあり、どこか楽しく練習を進めているように見受けられます。
大ヒットしたアニメの曲を弾く事になった小学生の生徒さんは、アレンジされた楽譜選びに少々手間取りましたが、最終的に当初選んだ楽譜を使う事になり、譜読みを続けています。ご本人が大好きな曲という事で、よく曲のイメージも捉えられており、「右手だけなら全部弾けるよ~」とノリノリで気分よく弾いています。ただ、ポピュラー系の曲は、ノリと雰囲気で曲を覚えていることが多く、それ自体はとても大切なものですが、それだけで弾いてしまうと、リズムなどが不正確で曖昧なまま覚えてしまっている箇所があることも多いものです。「なんか変だなあ」と弾いている本人も思っているようですが、ポピュラー系の曲はリズムが難しく、楽譜を見てもリズムを修正しにくいことがあります。
この生徒さんも、微妙な表情で弾いている箇所があちこちありました。楽譜でその個所を指しながら、少し説明をしましたが、その後は一緒に弾きながら体でリズムとタイミングを掴むような練習をしています。やはり、一緒に弾きますと曲の完成形が分かりますし、ずれてしまった時に、本来の正しいリズムや音楽の流れと自分の演奏の違いが把握しやすいと思います。この生徒さんも、レッスンの前半辺りまでは「ここ、難し~い」と弱音を吐いていましたが、何回も一緒に弾くうちに段々と掴めたようで、気が付けば黙々と弾いていて、だいぶご機嫌な様子に変化していました。
直ぐ後ろで聴いているお母様も、着々と本来の曲に近づいているのが嬉しそうですし、演奏が終わった時には1歳の弟さんがニコニコしながらパチパチと拍手をしていて、生徒さんは更に笑顔になっていました。このようなご家族の温かい雰囲気と応援が、生徒さんの励みになるんだなあと改めて感じた瞬間でした。
先程のお話で、おやつを食べそこなった生徒さんのお姉さんは、私が発表会の曲選びの時に「この曲はピッタリだし、きっと好きだろうから選ぶだろうなあ」と思いながら、発表会の曲をご紹介したところ、案の定その曲を選び、「やっぱり、この曲にすると思ったわ」と生徒さんとお話をして、「この曲いいよね~」と意気投合したところです。かなり気に入った曲らしく、1回目のレッスンからだいぶ楽しそうに譜読みをしていました。1音ずつ和音が低くなっていくところでは、どうしても最後辺りになると指がずれてしまい、「ええ~?」と自分で自分の指を見て驚きの声を上げながら、時には大笑いしながら弾くのですから、こちらもついつられて笑ってしまう事もあります。
曲の最後の辺りには、グリッサンドが出てきて、爪で鍵盤を撫でるような弾き方をしますが、「この部分は、グリッサンドのスタートとゴールの音が決まっているから、よく狙いを定めて弾いてね」と説明をして練習をしましたが、こちらも「ああああ」と叫びながらゴールの音を通り過ぎたり、慎重すぎてだいぶ手前の音で終わってしまったりと、いろいろとアクシデントがありました。ハラハラドキドキしながらではありますが、楽しいレッスンになりました。
このように、発表会の準備を進めつつ、春という季節がら新しくピアノを始められる方もおられて、体験レッスンも何回か行いました。
小学6年生の男の子は、家の近くのピアノ教室に通っていたそうですが、先生がお辞めになるタイミングでピアノのレッスンをやめたのだそうです。しかし、やはりピアノが弾きたいという事で、体験レッスンにいらっしゃいました。「とにかく楽譜が読めなくて」とおっしゃるので、使っているワーク教材を開いて、音名を聞きますとやはり苦戦していました。改めて確認という事で、基礎的な事や早く音を読むコツなどのお話をしました。その後、持って来た楽譜を出していただきますと7、8曲もあり、数の多さと共に、きれいに製本された楽譜にびっくりしました。
とにかくクラシックの曲が大好きなのだそうで、楽譜は読めなくても、先生の指の動きを見て覚えて弾いていたそうです。実際に、モーツァルトのトルコ行進曲を弾いてもらいました。弾きたいニュアンスをよく掴んでいて、読譜と指を強化していったら、なかなかステキに弾けるようになるのではと思い、体験レッスンでは、何箇所か強弱や弾き方の修正をして、「今後テクニックの練習をすると、もっともっと指が動くようになるので、こういう風に弾きたいというイメージに近い演奏ができるようになると思うわよ」とアドバイスをしました。その後も、大量に持ってきた弾きたい曲について、いろいろと話していて、本当に音楽が好きなんだなあと感じました。
残念ながら、その方よりも先にレッスン枠に入った方がいて、他の枠もご都合が合わないため、今回はご縁がなかったのですが、これからもピアノを好きで弾き続けてくれたら嬉しいなあと思いました。
別の日には、小学2年生の男の子が体験レッスンに来られました。小学校で鍵盤ハーモニカを演奏していて、とても好きそうなので、体験レッスンにいらっしゃったそうです。「鍵盤ハーモニカで、どんな曲を弾いていたの?」と聞きますと、カエルの歌を弾いていたそうで、早速ピアノで弾いてもらいました。しっかりと弾けていて、拍手をして「上手ね~」と声をかけ、「そういえば、カエルの歌の最初の音って、何ていうお名前だったっけ?」「ド」「そうよね。そのドって楽譜に書くと、こんな風になるんだよ」とワークの教材に繋げていきました。
その後は、「ド」だけを使った連弾の曲へと繋ぎ、ピアノにはドがたくさんあることや、右の方は高い音が出ること、左の方は低い音が出ることなども話しつつ、速さを変えたり、強さを変えたり、私が伴奏をペダルを使って演奏した場合と使わなかった場合で、その違いについて感想を聞いたり、最後には好きな強さとペダルの有無を自由に組み合わせて、連弾を完成させました。また、ペダルを使うとピアノの中がどのように変化するのか、ピアノの内部を見てもらい、立ったままですが実際に自分の足でペダルも踏んでみたりして、あっという間に体験レッスンを終えました。
帰りがけにも「体験レッスン、楽しかった!」と受付スタッフさんにも話していたそうで、数日後には入会することが決まり、来週から早速レッスンを始めることになりました。これからどのように成長していくのか、今から楽しみです。
最近の投稿
- お子様のピアノ発表会
- 世界を視野に入れ活躍する超新星
- お子様の発表会に向けた練習
- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間
- 春のお子様の生徒さんの様子
- ベートーヴェンが作曲家になる過程
- ヘンデルのお話
- 新しいクラシック
- どうぶつとクラシック
- オーケストラの日
カテゴリー
ブログ内検索
メールマガジン
音楽ナビ
con Vivace について
アーカイブ
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (3)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (3)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (5)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (6)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (2)
- 2011年5月 (3)
- 2011年4月 (2)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (1)
- 2010年8月 (4)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (54)
